脱炭素推進部門 教員紹介

部門長
人文社会科学研究科 教授
環境経済学・資源経済学
有賀 健高
地球規模の環境問題(温暖化・大気汚染・生物多様性破壊)を解決する制度や仕組みを研究するとともに、エネルギーや資源の持続可能な利用を促す経済政策、さらに行動経済学や心理学を活用し人間の行動変容を促す手法について探求しております。少しでも本学の脱炭素の取り組みに貢献していきたらと思います。

教育学部 教授
技術・情報教育、エネルギー・環境教育
山本 利一
学校教育に最先端の科学技術の仕組みを知らせる、教材・教具の開発を行っています。また、我が国に適した再生可能エネルギーの在り方を提案しています。一般的な、太陽光発電、風力発電に付け加え、海洋国家である我が国の特徴を活かした海洋エネルギーや地熱発電に関する研究を進めています。

理工学研究科 教授
植物分子生理学
西山 佳孝
光合成の環境応答メカニズムを分子生物学的手法で研究しています。また、藻類を用いたバイオ燃料の開発、有害赤潮藻の発生・衰退機構や魚毒性に関する研究にも取り組み、再生可能エネルギーの開発、海洋資源の保全、食料の安定供給といった持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献したいと考えています。

理工学研究科 教授
応用物性・結晶工学
矢口 裕之
次世代光エレクトロニクスへの応用に向けた半導体エピタキシャル成長、物性評価、デバイス化プロセス技術などに関する研究開発を行っています。脱炭素推進に関しては、高効率・低コスト次世代太陽電池に関する研究を行っています。

理工学研究科 教授
電力工学・高電圧工学
山納 康
大電力を安全で安心して利用するには、電気事故を未然に防ぐこと、仮に事故が発生して大電流が流れた場合には、人や機械を電気事故から保護する必要があります。そのためには電気事故が起きないように高い電圧に耐える能力が必要で、私は真空が持つ優れた絶縁性能を最大限引き出すための工学的な応用研究を行っています。また、大電流が流れたときに機器を保護するための高性能ヒューズの開発を行っています。

理工学研究科 教授
触媒化学・電気化学
荻原 仁志
触媒化学と電気化学を基盤にした、持続可能な分子変換プロセスの研究を行っています。たとえば、電気化学的手法を活用したアルコール類の高付加価値化を達成しています。今後は二酸化炭素や炭化水素といった分子を、社会に役立つ物質へと変換する反応系を開発します。

社会変革研究センター 教授
脱炭素・地球温暖化対策
加藤 直樹
「脱炭素先行地域(さいたま市,埼玉大学,芝浦工大,東京電力パワーグリッド)」の取組を通じた公・民・学の連携・共創により、それぞれが有する知見やデジタル技術などの先進技術を最大限活用しゼロカーボンシティならびにグリーンキャンパスの実現に向けた取組を推進します。

理工学研究科 准教授
エネルギー工学・半導体物性
長谷川 靖洋
廃熱を電気エネルギーに直接変換可能な熱電半導体の研究を進めています。熱電半導体の原理は簡便ですが、エネルギー変換効率が低いことが実用化のネックとなっているため、高効率化のための1次元量子ナノワイヤー熱電変換素子の開発を進めています。加えて、熱電半導体のエネルギー変換効率を簡便に測定するための新しい計測手法の開発も並行して進めています。

理工学研究科 准教授
高電圧工学・放電プラズマ工学
稲田 優貴
環境・医療・エネルギ向け放電プラズマを対象に以下の研究を行っています。(1)汎用性の高い先端的診断手法の開発(2)診断手法を駆使した新規現象の探索(3)現象理解に基づいた応用技術の最適化と新規実用化
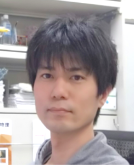
理工学研究科 准教授
半導体工学・太陽電池
八木 修平
半導体結晶成長と光・電子デバイス、特にIII-V族化合物半導体を用いた新規太陽電池の研究を行っています。太陽光エネルギーの利用効率の向上につながる研究により、脱炭素社会の実現に貢献します。

理工学研究科 准教授
無機材料化学
栁瀬 郁夫
二酸化炭素回収セラミックスとして安全・安価なナトリウムフェライトの開発を進めてきました。2025年現在、大阪・関西万博での実証試験が進行中です。今後は、大気中からの低濃度二酸化炭素を回収するべく、ナトリウムフェライトを超える優れた特性を有する無機材料の開発を推進していきます。

理工学研究科 准教授
センサ工学・生体計測工学
長谷川 有貴
植物自身の持つ植物生体電位応答から植物の生理活性状態などを把握する、新たなセンシング技術についての研究を行っています。この成果は、植物工場などの栽培施設の省エネルギー・高効率化などに役立ちます。また、脱炭素普及啓発活動の一環としてミニソーラーカー工作教室を随時実施しています。ご希望の方はご連絡下さい!

社会変革研究センター 准教授
環境計画
持木 克之
私たちが毎日使っている電気、上下水道、ガス等の生活インフラを中心に、環境に影響を与える過程の見える化、生活を考慮した環境影響の最適化、計画段階での環境影響評価を通じて、環境影響の最適化を図るための研究を行い、カーボンニュートラル社会の実現への貢献を目指しています。

社会変革研究センター 助教
電力工学
仲泊 明徒
再生可能エネルギーの大量導入に対応するための電力システムの運用・計画手法の開発に取り組んでいます。需要家側のエネルギーマネジメントや分散型エネルギーリソースの活用も視野に入れ、地域エネルギー社会の脱炭素化を目指しています。

