2025/10/30
【教育学部】住民の自治活動の理想形を探究
教育学部 学校教育教員養成課程 社会講座 高橋研究室
2025/10/30
教育学部 学校教育教員養成課程 社会講座 高橋研究室
自分たちが住むまちは、住民自らがつくる――。住みよいまちづくりのためには、行政の取り組みだけでなく、地域の人々が協力して課題を解決する「自治活動」が欠かせません。本学教育学部の高橋雅也教授は、そうした自治活動のより良い形を探る研究に取り組んでいます。
私の専門は地域社会学で、特に地域住民による自治活動を研究しています。自治活動とは、行政や外部のサービスに依存するのではなく、住民が「自分たちのまちをどうしたいか」を話し合い、力を合わせて行動する営みのことです。
たとえば、防犯や防災の取り組み、子育て世代の交流、伝統行事の継承など、日常生活のさまざまな場面に自治活動は息づいています。
さて、私は、まちづくりにおいて、自治活動は必要不可欠なものだと考えています。なぜなら、そこに住む人たちが活動を行うことで、「まちづくりを自分ごと」として捉えるようになるから。住民がまちづくりの意思決定にかかわることで、誇りや愛着が生まれ、ひいては安心で住みよい地域づくりにつながります。

近年、防災やオーバーツーリズム(観光客が増えすぎて生活や環境に悪影響を及ぼすこと)の問題が注目されています。こうした課題の解決に欠かせないのが、住民同士でどのように合意を形成していくかという点です。
同じ事象であっても、立場によって考え方は異なります。たとえばオーバーツーリズムに取り組もうとした場合、飲食店を営む人にとっては観光客が集まることは歓迎すべきことですが、静かに暮らしたい住民にとっては好ましくない場合もあります。
こうした意見の違いがあることを前提に、地域の自治活動の枠組みを通じて、丁寧に話し合いを重ねながら合意をつくっていくことが大切なのです。
しかし現代では、自治活動の担い手不足が深刻です。高齢化に加え、「行政や企業に任せればよい」という考えで、活動に参加しない人が増えているからです。
一方で、若い世代の中には「面白そうだからやってみたい」と新しい関わり方を模索する人々もいます。ある地域では、若い人たちが中心となり、回覧板をやめてSNSで情報を共有する取り組みを始めています。こうした工夫が、自治活動に新しい活力をもたらすこともあります。
私の研究方法は、地域の活動に直接参加し、住民との対話を記録する質的調査が中心です。夜間の見回り活動などに同行し、その後の話し合いまで耳を傾けることで、安全性や信頼関係がどのように育まれているのかを理解します。こうした取り組みによって、さまざまな事例を集め、多様な地域で応用できる「居心地の良い自治」のモデルを描くことが目標です。
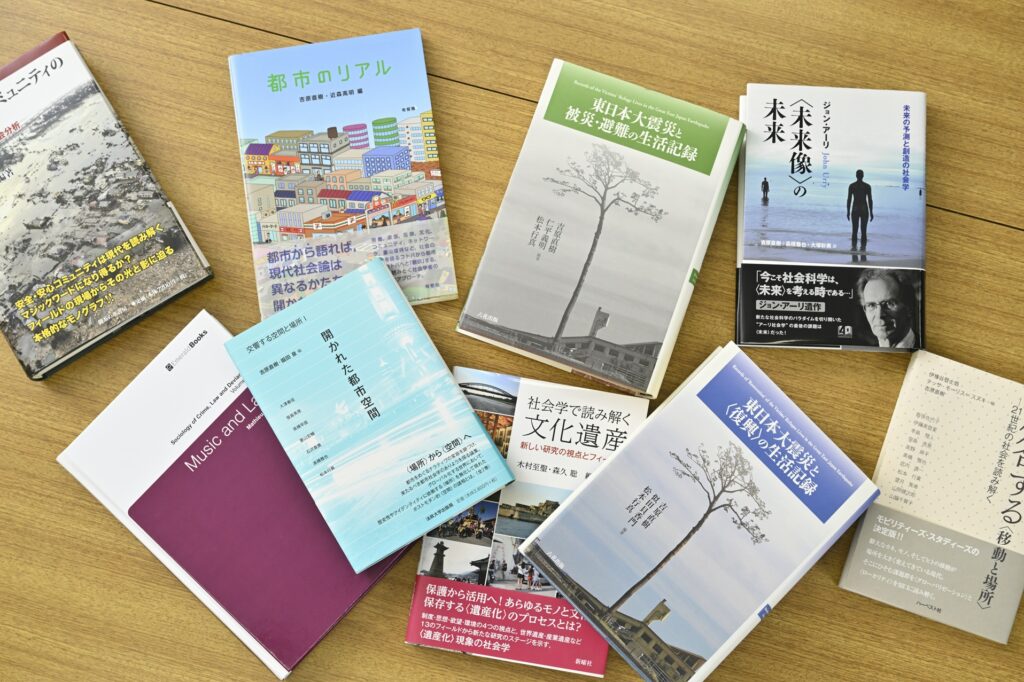
研究を続ける中で、各地域で「知恵者」と呼ばれる方に出会ってきました。災害時に住民たちを安全に避難させた長老、地元に戻った人々を受け入れるため工夫を重ねた祭礼の担い手、データに基づく根拠を行政に示すことで自分たちの要望を実現させた住民たち。こうした人たちとの交流からさまざまな学びが得られることが、この研究の最大の魅力です。
一方で、情報化社会では「自分がどう評価されるか」を意識する人が増え、本音を聞き出すことが困難になっています。だからこそ、何度も足を運び、丁寧に信頼関係を築くことが重要です。調査に協力してくれる人たちに「この研究者は他と何か違うな」と思ってもらえた時に、初めて本音が見えてきます。
これまでには、東日本大震災に関わる研究を行いました。自主避難者が新しい地域でどう生活を築いているか、震災遺構をめぐる住民合意の形成など、災害と地域社会の関わりを多角的に分析した実績があります。
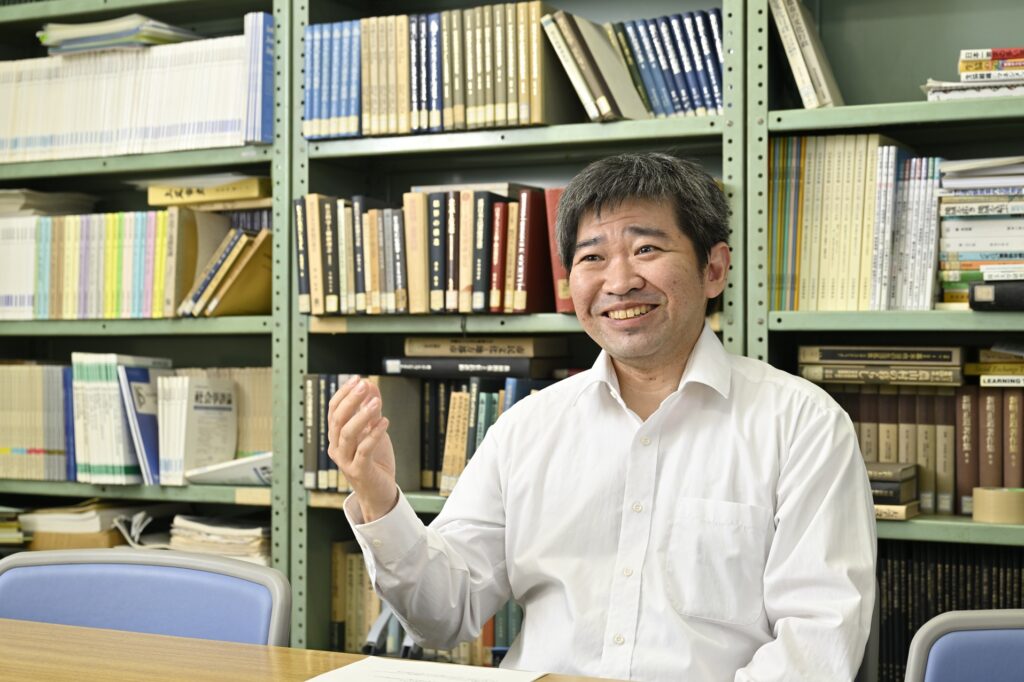
私の研究は、地域住民だけでなく、行政や企業が地域とどう関係を築くかにも示唆を与えるものです。自治活動は住民だけでは成り立ちません。行政や企業といったプレーヤーも含めて、互いの論理を理解し、水平的につながることで、より良い地域社会が実現するのです。私の研究は、いわば、そのための「知恵の集積」を目指すものといえるでしょう。
今後は、「強制ではなく自然に人が関わりたくなる仕組み」をいかにつくるか? その方法論を探究していきたいと考えています。担い手を無理に育成するのではなく、自然と自治活動に参加したくなる環境をデザインし、それを次世代へと伝えていきたいですね。