2025/01/28
【教育学部】これからの国語教育をどう充実させていく?
教育学部 学校教育教員養成課程/本橋研究室
2025/01/28
教育学部 学校教育教員養成課程/本橋研究室
本学教育学部の本橋幸康准教授は、国語教育の充実に向けて、主に昭和20~30年代の日本で行われた国語教育の取組を掘り起こす研究に取り組んでいます。過去に行われた教育の試行錯誤の過程から学びのヒントを探索するという研究とはどのようなものなのか。本橋准教授にお話を伺いました。
国語という科目について、「何を学んでいるかわからない」という印象をもつ子どもは少なくありません。また「何を教えたらよいのかわからない」という悩みをもつ先生の声もよく耳にします。
これらの課題の解決を目的に「国語の学力とは何か」「これまでの国語の授業ではどのような学力を育んできたのか」などを考察する「国語学力論」と、実際にどのような指導を行えばよいのかという「学習指導論」についての研究を行っています。
具体的には、学力調査等を活用しながら、国語教育における児童・生徒の実態や課題を把握。そこから国語での学びが他の教科や日常生活で活用できることを実感できる授業のカタチを現職の先生方と一緒に考えていくのです。
なお、私の研究では、歴史的な観点を取り入れているのが特徴の1つ。簡単にいえば、これまでの国語教育に関する理論研究や過去に行われてきた教育実践を踏まえて、国語科の授業づくりを研究していきます。
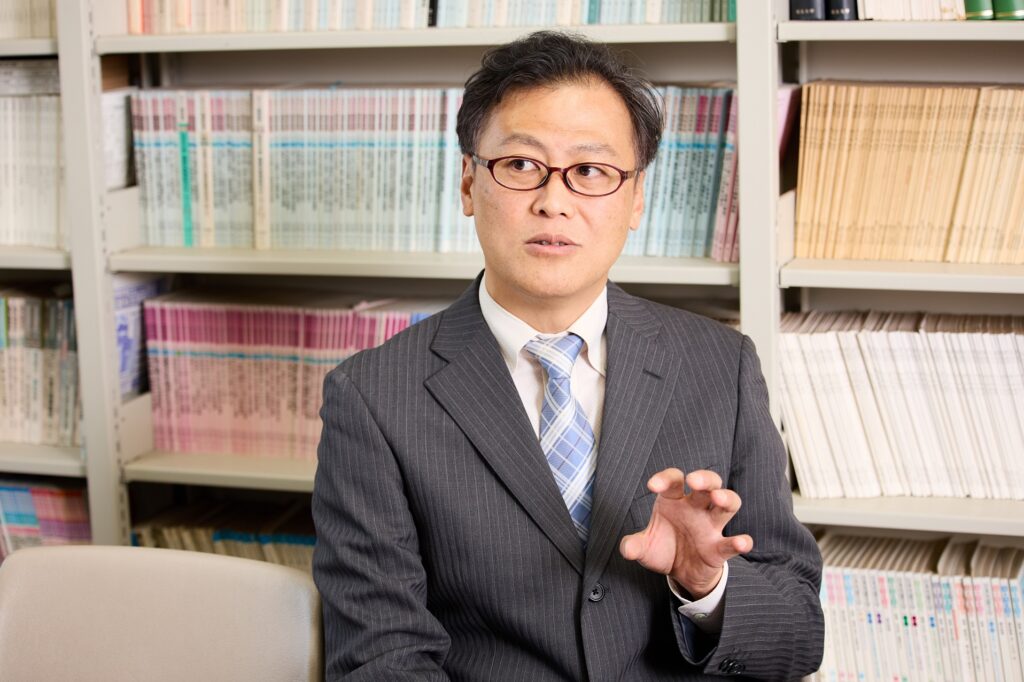
例えば、昭和20年代は、文部省(現在の文部科学省)が「下の方からみんなの力で、いろいろと、作りあげて行くようになって来た(『学習指導要領一般編 試案』昭和22年)」というように、全国各地で特色ある授業が行われていました。現場の先生方が、少しでもよりよい学びを子どもたちに提供するために、様々な工夫を凝らしてきたのです。
国語の授業では、教科書だけではなく、児童の身近な生活や地域の実態に応じた題材を用いて、調べたり、話し合ったり、発表したりという具合です。今でいう「総合的な学習の時間」のイメージに近いかもしれません。国語で学んだことを日々の生活に活用していくといった視点があります。
ただ、こういった当時の取組は、ほとんど顧みられることなく、資料なども図書館の書庫などに埋もれているのが現状。そこで、北海道から沖縄まで、現地の図書館や学校に足を運び、資料を掘り起こしていくのが研究の第一段階です。そして、資料の内容を整理し、教育史の観点から価値づけていきます。さらに、取組における試行錯誤の過程など、研究で得られた知見を現職の先生と議論・検討する際のヒントにしていくのです。もちろん、過去に答えがあるわけではありません。実態や課題、取組の実践を含めて共有し、今の授業づくりに活用していくのです。
このような活動の他、埼玉県教育委員会と連携し、学習改善、授業改善を目的とした「埼玉県学力・学習状況調査(埼玉県)」や「全国学力・学習状況調査(文科省)」などの結果を活用して授業を充実させる取組を行ったり、小中学校の国語の教科書や小学生向けの国語辞典の編纂などにも携わったりしています。
国語教育の道に入ったのは、大学院時代の恩師から「言葉を研究することは、人間研究そのものだね」といわれたのがきっかけでした。それまでは日本語学の研究をしていましたが、この言葉を聞いて、教育という観点から言葉を捉える研究に従事したいと強く思ったのです。
それ以来、中学・高校国語の教員や行政(国立教育政策研究所)などを経験しながら、教育史の観点も含めてさまざまな先生方の授業づくりの工夫を現場の先生方と共有し、子どもはもちろん、先生方も楽しむ授業づくりの研究に取り組んでいます。
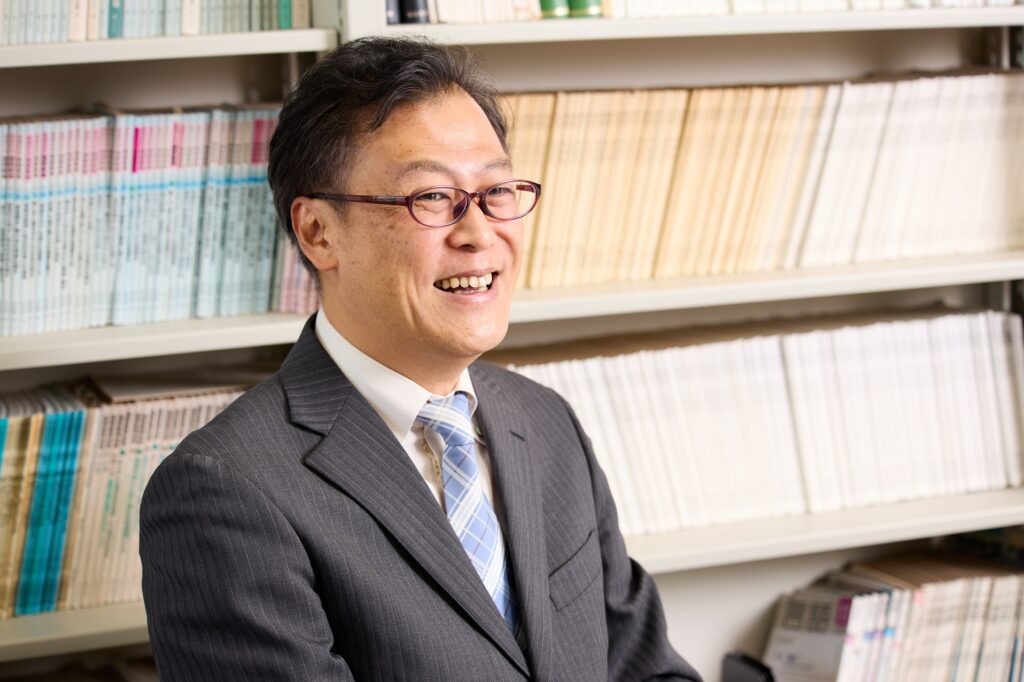
これからますます学習の過程を重視した教育が求められていくでしょう。自らが導き出した答えを価値付け、意義付けていくためには、どのように試行錯誤したか、そのプロセスが重要になってきます。学習の過程を充実させることが、自らの成長や学びの広がりや深まりを実感することにつながり、学習意欲の向上につながります。ただ、現代の教育を語るこうした考えも実は昭和30年代にすでに指摘されていたことでもあります。学習過程を適切に評価することが、自らの成長や学びの広がりや深まりを実感することにつながり、学習意欲の向上に寄与するのはいうまでもありません。
これからも全国各地に眠る資料の調査を続けて教育史に学び、現職の先生方とこれからの国語教育の充実に向けて探究していきたいですね。そのような活動を通じて、教育において自身の成長を実感することの重要性が社会に広がればよいと考えています。