数理を用いて機械学習の進化を図る
~情報処理技術の革新的アルゴリズムを開発~
Frontiers of SU Research
理工学研究科 大久保 潤


電力消費量の増大など、人工知能にまつわる課題の解決に挑む研究者がいる。理工学研究科の大久保 潤教授だ。「研究によって、数理に基づく新たな情報処理技術が確立できれば、コンピューティングの世界をガラッと変えられる」と強調する大久保教授に取り組みの内容を聞いた。
AIの未来を変える、数理に基づく情報処理技術とは
現在、人工知能(AI)の活用が進む一方で、いくつかの問題が顕在化している。
例えば、機械学習には大量の学習データが必要であり、その学習と実行には高性能なハードウェアと膨大な電力が求められる。また、AI解析では「なぜその結果が得られたのか」が不明確であることも大きな課題の1つだ。
私が取り組む研究は、このような課題を解決するもの。数理的アプローチを用いて、新たな機械学習のアルゴリズムを構築しようとしている。
機械学習は、与えられたデータを学習し、新しいデータに対する予測結果を導き出す。しかし、その処理過程はよくわからない。もし処理過程を方程式の形で書き下せれば、「機械学習でなぜその結果が出たのか」が説明可能になる。そこで、「双対性」や「クープマン(Koopman)作用素」といった数理を応用し、機械学習結果の内部を解析するためのアルゴリズムを開発しているのだ。
この研究の成果は、特にクリティカルな業務や安全性が最重要視される業務へのAI活用の途をひらくことにつながる。
例えば、造船のような現場では、ちょっとした判断の誤りが人命にかかわる大事故につながりかねない。そのため、AIがどのように判断を下したのかが明確でなければ、業務に活用することが難しい。その点、私が開発した手法であれば、処理過程が可視化されるため、こうしたミッションクリティカルな領域への利用が可能になる。
さらに処理過程の可視化によって、学習に有効なデータの素性も明らかになると期待される。結果として、必要最低限の学習データで有効な結果を導き出すことが可能になる。
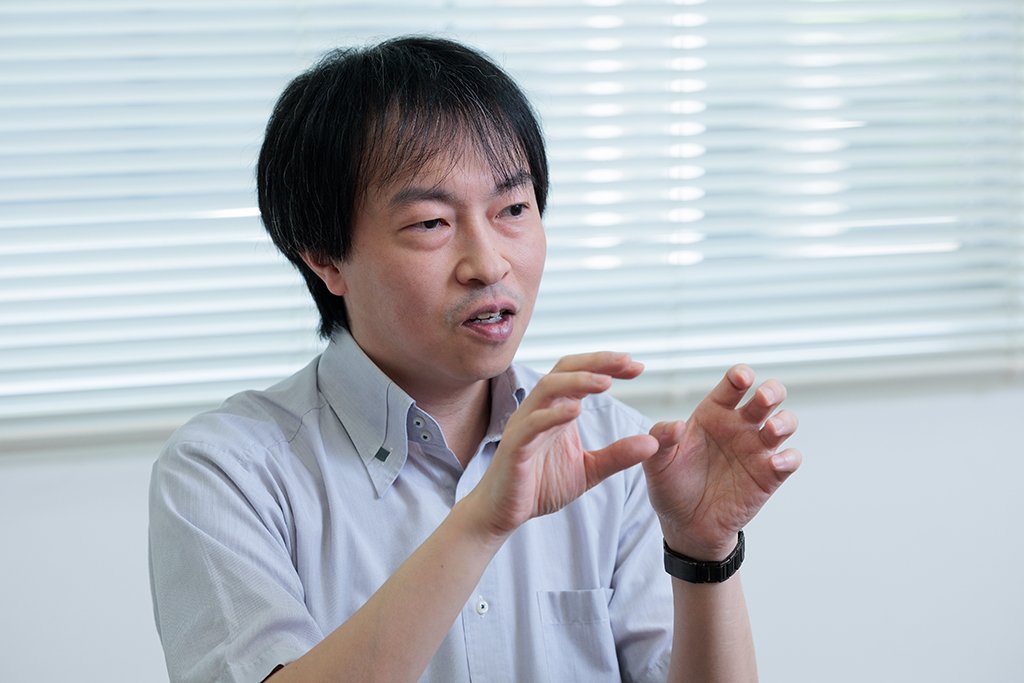
最近の研究では、方程式の事前情報を学習に組み合わせることで、10件程度の学習データにより、高精度な将来予測が実現可能であることを確認した。完璧な事前情報は不要で、ある程度のもので問題ない。データだけではなく、他の情報と組み合わせることによって、「機械学習には膨大なデータが必要」とされてきた従来の常識を打ち破る可能性が見えつつある。
学習データが少なくて済めば、情報処理のスピードや工数は大幅に短縮され、インフラへの負荷を軽減させ、消費電力の抑制につながるというわけだ。
話題の光回路や量子コンピュータ関連の研究も
次世代技術の実現に向けた研究にも力を入れている。
現在、取り組んでいるのが、次世代コンピューティング技術として期待される「光回路」技術の応用に向けた研究だ。これは線形代数(行列)の理論を使って、ニューラルネットワークの構造を簡素化し、光回路が得意とする形へと変換するものである。
また、過去には大手システムベンダーと「アニーリング型専用ハードウェア」に関する共同研究にも取り組んだ実績も。このプロジェクトでは従来は処理が難しかった「不等式制約付きの問題」を、数理的な変換によって処理可能にするプログラムを開発。ハードウェアの変更を伴わず、数理アルゴリズムのみで解決させたことは、ハードウェア側の追加投資を抑えられる点で、大きな意義があったと考えている。
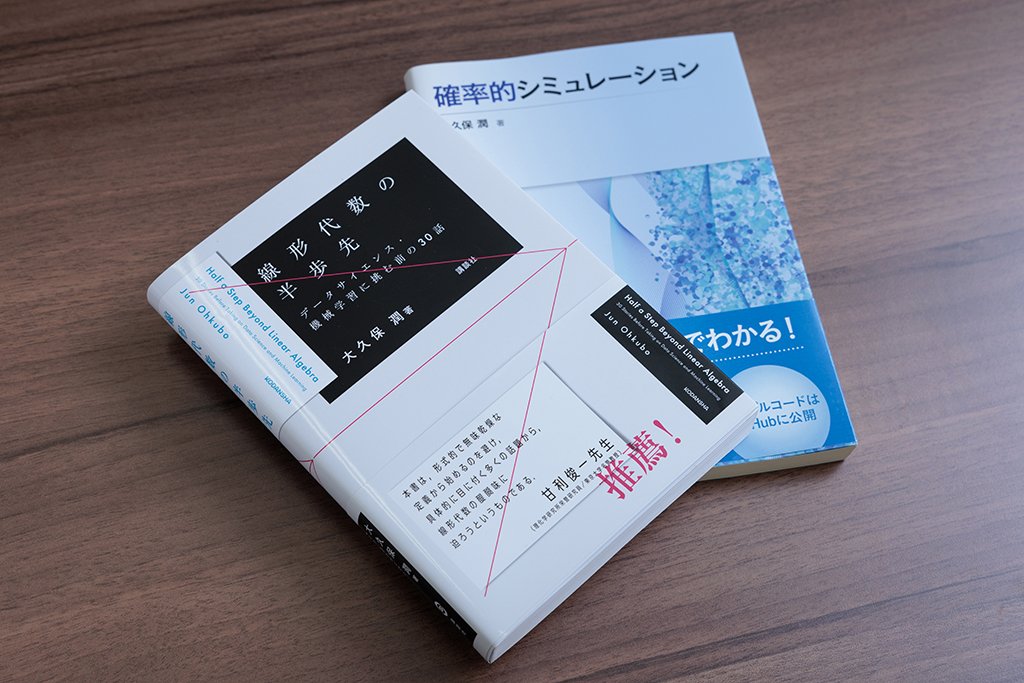
プロセッサなど、ハードウェアの進化が頭打ちになりつつある現在、プログラム側の革新がより重要になるだろう。数理を活用して情報処理技術を進化させることで、コンピューティングの世界をガラッと変えられると確信している。
社会実装に向けては、さらなる高精度化や処理効率向上のための実証研究が求められる。実際の活用シーンにおける課題や制約を共有し、それをともに解決していく共同研究パートナーの存在が不可欠だ。
今後は、さまざまな業種・業界の技術者や研究者と連携しながら、現実の課題に応える応用技術の確立を目指していきたい。
本研究との産学官連携にご関心のある方は、こちらのフォームへお問合せください。
大久保潤(オオクボジュン)研究者総覧

