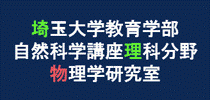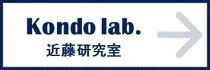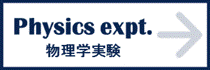このページは、物理学実験履修者に向けたページです。
基礎実験
■§5 ノギス
| 目的 |
ノギスを用いて中空円筒の体積を測定すること。
|
|---|
| 測定する値 |
円筒の直径・円筒の高さ・円筒の質量
|
|---|
| 算出する値 |
円筒の密度
|
|---|
| 検討すべき値 |
円筒の素材であるアルミニウムの密度と算出した円筒の密度
|
|---|
| 実験に使用するもの |
ノギス・電子天秤・金属円筒
|
|---|
| 注意事項 |
試料の素材はアルミニウムである。
この実験で密度を測定するのは、試料の素材を決定するためではなく、
正しく円筒の体積を測定できたかを確かめるためであることに留意する。
ノギスのねじを締めない。
ノギスは測定するものにあてたまま目盛りを読むこと。
目盛りの読み方に注意する。
|
|---|
| その他 |
ノギスの読み方(pdf版)
|
|---|
■§6 マイクロメーター
| 目的 |
マイクロメーターを用いて、与えられた針金の直径を測定すること。
|
|---|
| 測定する値 |
針金の直径
|
|---|
| 算出する値 |
|
|---|
| 検討すべき値 |
ワイヤーゲージで得られた値の範囲と
測定した針金の直径
|
|---|
| 実験に使用するもの |
マイクロメーター・ワイヤーゲージ・針金
|
|---|
| 注意事項 |
ワイヤーゲージの規格はB.W.G.である。
ワイヤーゲージは、各番線の穴に通すだけでなく、
穴の切れ目から軽く外に抜けるかどうかで判断することに留意する。
マイクロメータは零点補正(測定前に何もはさまない状態で目盛りを読み取ること)を、
毎回行うこと。
機器の調整は済んだものとする。教員の許可なく付属のレンチ等を使用した機器の
調整の変更を行ってはいけない。
マイクロメーターの細い部分のつまみを持ってねじを締めること。
そのほかの部分を持ってねじを締めてはいけない。
測定するものに当てたまま目盛りを読むこと。
|
|---|
| その他 |
|
|---|
■§7 球面計
| 目的 |
球面計を用いて、球面レンズの曲率半径を測定すること。
|
|---|
| 測定する値 |
球面計の脚の距離・球面計の読み(平面上・球面上)
|
|---|
| 算出する値 |
球面レンズの曲率半径
|
|---|
| 検討すべき値 |
球面レンズの曲率半径
|
|---|
| 実験に使用するもの |
球面計・ノギス・球面レンズ
|
|---|
| 注意事項 |
球面計の脚3つ全てがレンズの上に乗るようにすること。
全ての脚がレンズの外にある場合、曲率半径ではなく、厚さの測定になる。
球面計の脚と脚の距離は、ノギスを用いて測定すること。
測定する面が凸面か凹面かを考えること。
目盛りを読む際は、外側の目盛り(黒字)か
内側の目盛り(赤字)かを考える。
どちらの目盛りを読んだかノートに記録すること。
|
|---|
| その他 |
|
|---|
■§8 Amslerの面積計
| 目的 |
Amsler形面積計を用いて与えられた面積を測定すること。
|
|---|
| 測定する値 |
2つの腕の長さ・支軸と動輪の距離・動輪の直径・
面積の分かっている大小2つの長方形の回転数・
面積の分からない閉曲線の回転数
|
|---|
| 算出する値 |
機械についての定数・機械の零円の面積・
閉曲線の面積
|
|---|
| 検討すべき値 |
機械についての定数k1とk2・kとk
零円の面積S'0とS''0・S0とS0
閉曲線の面積SとS'とS''
(当日配られるプリント参照)
|
|---|
| 実験に使用するもの |
Amsler形面積計・ノギス・定規
|
|---|
| 注意事項 |
当日配布するプリントにしたがって結果の検討を行うこと。
値を計算式に入れるときの符号に注意すること。
原理的に動輪Cが止まっていることがある。それはどのような場合か理論にもとづいて考えよ。
ノギスで測ることが難しいところは定規を使うこと。
方眼紙の目盛りを読むときは、数え方とその記録をきちんとレポートに書くこと。
mm方眼紙の最小目盛は1mmであるので読みとり誤差は0.1mmである。
|
|---|
| その他 |
配布資料データ(pdf版)
Amsler読み方(pdf版)
|
|---|
■§9 天秤
| 目的 |
(1)与えられた天秤の感度曲線を作ること。
(2)与えられた物体の質量を測定すること。
(3)空気の浮力補正を行うこと。
|
|---|
| 測定する値 |
天秤が振れたときの左右の目盛り・与えられた物体の質量(電子天秤測定)
|
|---|
| 算出する値 |
与えられた物体の質量(天秤測定)
|
|---|
| 検討すべき値 |
電子天秤で測定した物体の質量と天秤で測定した物体の質量
|
|---|
| 実験に使用するもの |
天秤・分銅・電子天秤
|
|---|
| 注意事項 |
得られた静止点の値で他とずれた値があった場合、
もう一度測定すること。
分銅や試料を皿にのせるときは、必ず取っ手を静かに反時計回りに回して
皿を固定すること。
感度は毎回計算して、グラフに描きながら測定すること。
ただし、測定点を直線でつないではいけない。滑らかに書くこと。
|
|---|
| その他 |
1人での実験は不可能。2人で行うこと。
方眼用紙を持参すること。
|
|---|
■§11 回折格子の作製
| 目的 |
写真フィルムを使って回折格子を作製すること。
|
|---|
| 実験に使用するもの |
カメラ・フィルム・現像液・停止液・定着液・
光源(He-Neレーザー)・スクリーン・メジャー
|
|---|
| 注意事項 |
薬品の取り扱いや暗室での作業があるので教員・TAの指示をよく聞いて従うこと。
|
|---|
| その他 |
実験プリント(pdf版)
|
|---|
■§13 Bordaの振り子
| 目的 |
Bordaの振り子を用い、その地の重力の加速度gを測定すること
|
|---|
| 測定する値 |
振り子の針金の長さ・球面体の直径・エッジの周期・
振り子の周期・コンピュータで計測した周期
|
|---|
| 算出する値 |
重力加速度g
|
|---|
| 検討すべき値 |
教科書記載の重力加速度の値と
コンピュータ計測で得られた重力加速度の値と
算出した重力加速度の値
|
|---|
| 実験に使用するもの |
Bordaの振り子・望遠鏡・ストップウォッチ・メジャー・
ノギス
|
|---|
| 注意事項 |
100Tの値について2秒近くの差があった場合、1周期分の数え間違いをしているので
やり直すこと。
針金の長さは、メジャー2本を用いて測定すること。
このとき、おもりは吊るしたまま測定する。
周期を測定し終わったら、最後に
コンピュータによる周期の測定を行うので申し出ること。
|
|---|
| その他 |
|
|---|