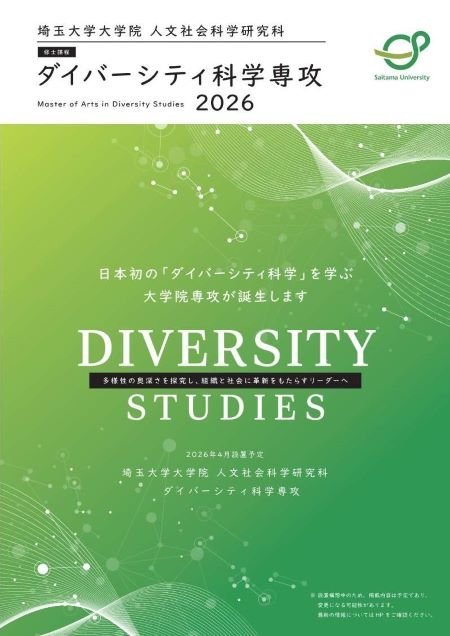ダイバーシティ科学専攻について
ダイバーシティ科学とは ―「違い」がつむぐ共生の知へ―
ダイバーシティ科学とは、多様な差異が社会や組織に与える影響を科学的に探究し、歴史的・社会的文脈における差別や格差のメカニズムを解明する、学際的かつ先駆的な研究分野です。ジェンダー、セクシュアリティ、民族、障害、年齢、文化的背景など、人間の多様性を尊重し、その違いが差別や排除の原因とならない社会構築のために、理論と実践を架橋する視点を提供します。
さらに本専攻は、多様性を単に受け入れるべき「違い」として捉えるのではなく、社会を豊かにし、人と人とを結びつける創造的な力として積極的に活かしていくことを重視します。多様な経験や視点から生まれる知識と実践は、複雑な社会課題に向き合うための、多角的かつ柔軟なアプローチを生み出します。
本専攻では、社会科学・人文科学を基盤に、教育、福祉、法、政策、そして科学技術など多領域にまたがるアプローチを通じて、すべての人の人権とウェルビーイング(幸福)が尊重される包摂的かつ公正な社会を目指します。現場との対話や実践を重視し、ダイバーシティをめぐる課題解決に取り組む研究者・実践者の育成を目指すことも、本専攻の大きな使命です。ダイバーシティ科学は、違いを力に変え、多様な人々が共に生きる社会の実現を目指す挑戦的な学問です。
新たな学問の地平──ダイバーシティ科学への招待
副学長(ダイバーシティ推進担当)挨拶

ダイバーシティ、すなわち多様性を中心に据えた学術的探究は、すでに海外の大学院教育において一定の体系を持ち、社会変革を担う人材を輩出しています。本専攻は、こうした国際的な動向に呼応し、日本で初めて「ダイバーシティ科学」を専攻名に冠した、大学院レベルの研究教育の場として誕生します。
いま世界では、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)=DEI
を軸に、社会のあり方を見つめ直す動きが加速しています。ダイバーシティ科学は、人々の違いを排除の根拠とするのではなく、社会を豊かにする力として、多様性の価値を実践にいかす新しい学問領域です。
一方、日本社会では、ジェンダー平等、障害者の権利、移民・難民への対応など、多くの課題が未解決のまま残されています。私たちは、こうした複雑な現実に向き合いながら、一人ひとりの人権とウェルビーイング(幸福)が大切にされる、誰もが安心して生きられる公正な社会の構築を目指します。
本専攻では、社会科学と人文学を基盤に、多様な分野の知を組み合わせ、現場との対話と実践を通じて課題解決に取り組みます。そしてもう一つの大きな特徴は、仲間と協働しながら実践を創造していく学びのスタイルにあります。
多様な背景や価値観をもつ人びとが対話を重ね、異なる視点をすり合わせながら共通の課題に向き合う過程は、ときに困難をともなうものです。しかし、議論を積み重ね、互いに学び合いながら、共に変わっていくプロセスそのものが創造的で、未来を切りひらく希望に満ちた営みです。
ダイバーシティ科学は、すべての人の可能性を信じ、多様性を祝福する学問です。この専攻が、誰もが輝ける社会をともに築く出発点となることを願っています。
令和7年4月
埼玉大学副学長(ダイバーシティ推進担当)
田代 美江子
パンフレット
クリックするとPDFで開きます